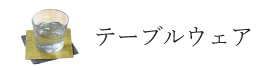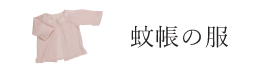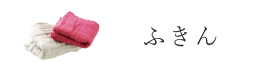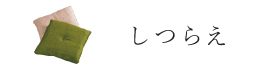春近しの掛け声ばかり高く、今日も雪のちらつく空模様です。
明日は修二会の大松明が二月堂の舞台を駆け回ります。
私の娘時代、東大寺観音院へ毎々遊びに伺いました。
父が観音院住職の上司海雲さんと懇意であった頃から
連れられて始めは行っていたのですが、その内大きくなってからは
海雲さんの人間性に惹かれていろいろな会のお手伝いに行ったり
奥様にお茶のお稽古をしていただいたりとよく伺うことになりました。
骨董品の交換会である「我楽苦多(がらくた)会」が毎月観音院で催されたり
遊びの会があったりと、いつも人の出入りが多く、にぎやかなことが好きな海雲さんでしたが
信仰という点においては大変真摯な方でした。
年に一度の修二会の行には管理職になられるまで必ず毎回欠かさず籠られていました。
2月20日からの試別火から3月13日の満行までの20日あまりの荒行に毎年出仕されるお姿は
日頃、私たちに接されるやさしい態度とはまったく別の厳しい面を持っておられました。
修二会のお松明が上堂する頃、私も2度ほど局部屋で籠ったことがありました。
二月堂内、十一面観音様の周囲で錬行衆の僧侶が祈りの行をされている
その外陣の一角にある局部屋には行儀に座った人でいっぱいの中、一夜を過ごします。
無心になって祈る中、内陣の僧侶の読経の声と松明の明かりと駆け回る足音が
現代の私たちを1200年以上前から続く幽玄の世界へ誘います。
遠い昔の思い出です。
3月13日の午前2時頃若狭井(閼伽井屋)からお水(香水)をくむ行事があり
これがお水取りの別名ともなった由縁です。
その深夜、達陀の妙法が行われ、ようやく奈良にも春が訪れます。